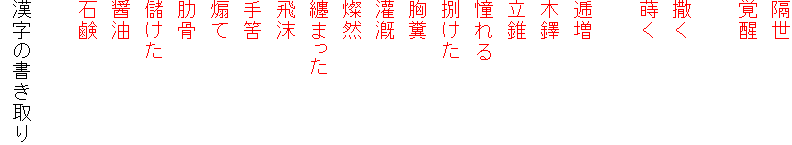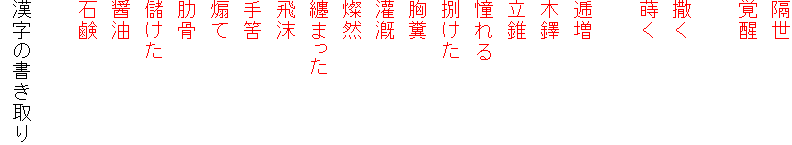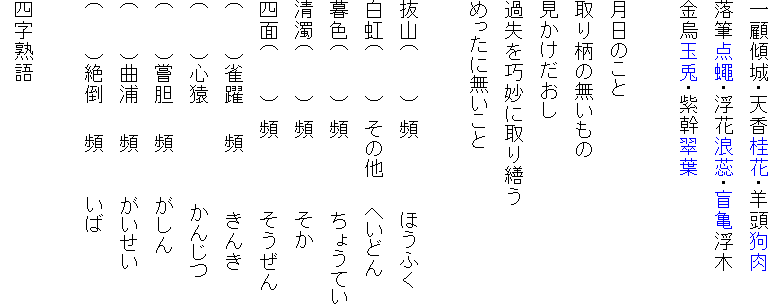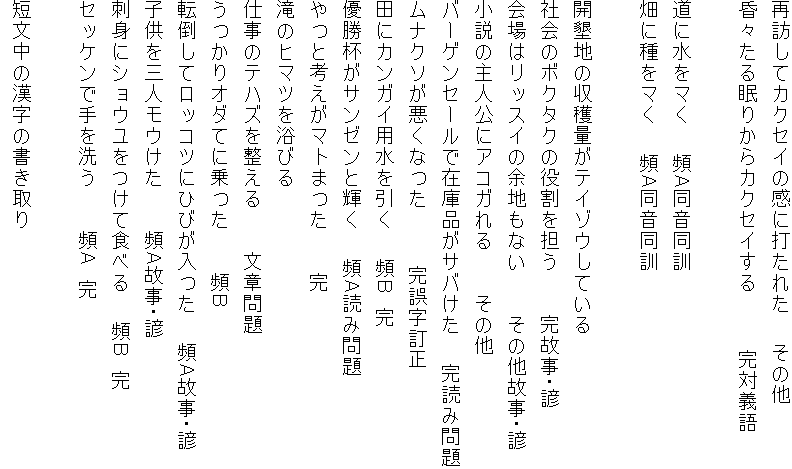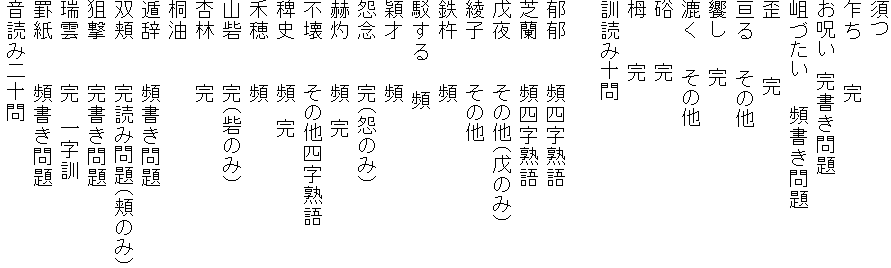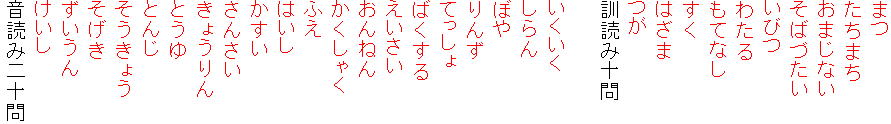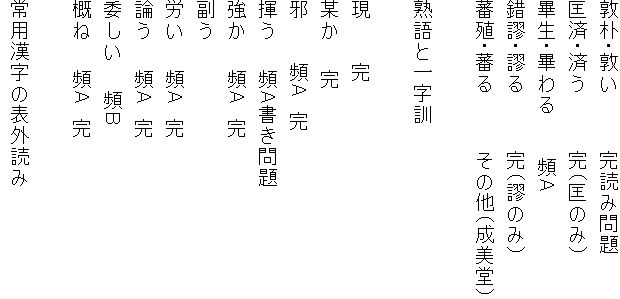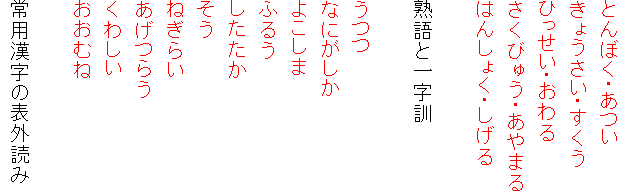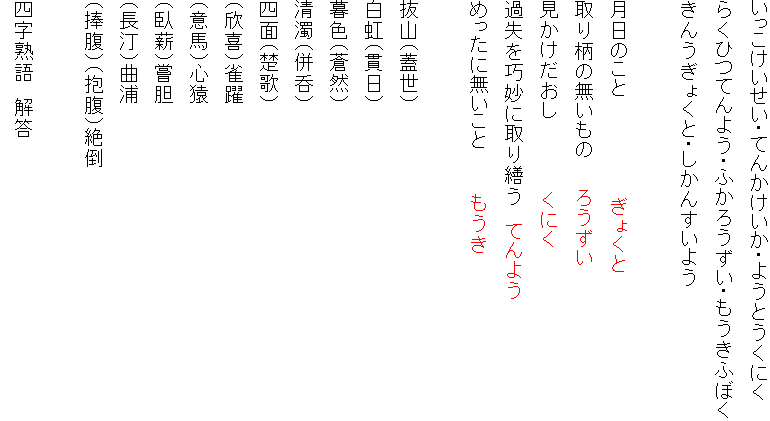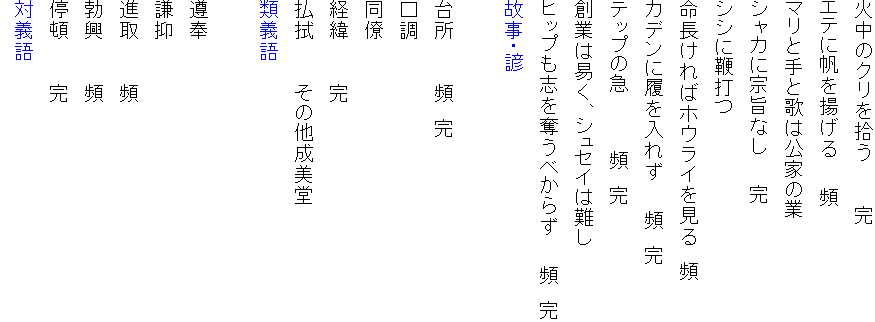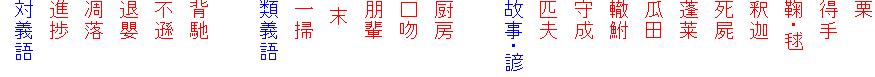2008年第3回の準1級検定試験の問題です。(一部許容字体を使っております)
この回の難易度が高かったかどうかはわかりませんが、初めて見る問題が結構ありました。
また問題には準1級配当漢字がほとんど使われるのだろうと思っていたのですが、書き問題で「逓増(ていぞう)」という2級の配当漢字が、四字熟語では「意馬心猿(いばしんえん)」というこれも2級で勉強した四字熟語が出ていました。逓増は2級の時逓減という問題を良く解いていましたが苦手な漢字でした。案の定、逓の横線を1本にしてしまい不正解。「意馬心猿」は2級の分野別問題集で1回だけ解いたことのある四字熟語でした。いばの部分が抜けていて、馬はわかったのですが意がどうしても思い出せなかった・・・。仕方なく「異」と書き不正解。両方できなかったのは情けない限りです・・・。
読み問題の印象は、割りに易しい印象です。8問目の「山砦」はいつも「城砦」という問題を解いていましたが、この日なぜか急に「砦」が出てこなく後回し。見直し時に「城砦」という熟語を思い出してセーフ。「鉄杵((てっしょ)」もいつもは「杵臼(しょきゅう)」という熟語で解いていました。「杵臼」については「臼杵」という問題もあり最初混乱しましたね。杵の音読みがしょなのかきゅうなのか覚えるのに少しかかりました。
要注意は「綾子(りんず)」あやこではありません(笑)これは試験1週間前の再チェックで引っかかっていました。再チェックしていなければ答えられなかった問題です。きっとダメ元であやこと書いていたかもしれません。
そして1問だけ落としてしまった「須(ま)つ」これは訓読みが5つもある漢字です。普通「須(すべから)く」という問題が多いので、それはチェックしていましたが(まつ)と読むとはしりませんでした。だめだこりゃと思いながら「すだつ」と書いて不正解。あとは「歪」も要注意ですね。歪む(ゆがむ・ひずむ・いがむ)と同じ送りでも3つの読み方があり問題の文章に見合う読みを選ばなくてはいけません。、おくり仮名なしの場合は(いびつ)、これは問題やっていたので解けました。
私が受けた試験問題の一部です。問題下にはどの問題集で学習したか書きました。
頻=頻出度別問題集 完=完全征服 その他=他の5冊から
表外読みの問題は、
頻出度別問題集、
完全征服からほとんど出題されました。比較的答えやすい問題が多かったように思います。「副う」は一度だけ何かの問題集で解いていましたが、探しても見つかりませんでした。これは問題文を読めば何となく「そう」と答えられるように思います。
熟語と一字訓についても、問題集に良く出ている問題でしたが、敦朴は淳朴で出ていることがほとんどです。敦は敦厚という問題で良く出ています。要注意ですね。錯謬は問題集では「誤謬・謬る」が多いですが「錯」が読めればまず大丈夫でしょう。匡済はひねり問題ですね。「匡正」では良く出てきますが「済う」との組み合わせは初めて見ました。難しかったのは「蕃殖・蕃る」ではないでしょうか。これは
成美堂本試験型の第16回問題で1回だけ解きましたが、6冊の問題集で1題だけでした。
書き問題については、頻出度別問題集、完全征服からかなり出題されていましたが、書き問題以外の分野の熟語も多く書き問題として出題されています。「逓増」については2級の配当漢字です。準1級配当漢字と問題に出てくる常用漢字しか頭になかったのでこの「逓増」は書けませんでした。2級の学習で逓減という熟語を覚えましたが「逓」という字が本当に苦手でした。当日も逓の横線2本を1本にしてしまい不正解です。まさに意表を突かれた思いです。
●四字熟語
四字熟語は成美堂本試験型の付録に約290の四字熟語が掲載されています。6冊の問題集で出題された四字熟語はすべてマーカーで潰していましたが、マーカーされていない四字熟語が40くらい残りました。マーカーで潰し240から250は覚えましたが、白虹貫日(はっこうかんじつ)は白く残っていた四字熟語です。浮花浪蕊、天香桂花、紫幹翠葉も知らない四字熟語です。浮花浪蕊は消去法で残って読めましたが書くのは無理だったと思います。
対義語・類義語は覚えやすくまた覚えられた分野でした。どの問題でも割と満点を取れていました。検定でも全問解けています。「謙抑」「遵奉」については初めて問題です。選択にふそんとあり、謙虚⇔不遜という問題を思い出して書けました。「遵奉」についても初めて問題でしたが、これは選択肢が「はいち」のみ残ったので「背馳」と書きました。遵(したがう)に対して背(そむく)です。
故事・諺では、学習中、「死屍に鞭打つ」をよく獅子と間違え、当日もはじめ「獅子」と書いていましたが残り5分の見直しで間違いに気づき「死屍」と書き直しました。シュセイは答えられませんでした。「殊成」と書いて不正解です。
>トップに戻る